🔍️ Trovi similajn vortojn 似た単語を表示
エスペラント界最大の組織である UEA(Universala Esperanto-Asocio) は、近年国際機関への働きかけと内部改革の双方で活発に動いています。例えば、UEAは国連やUNESCOの「国際〇〇デー」に合わせて多言語教育や文化多様性を訴える声明を発表し、エスペラントを言語権擁護の観点からアピールしています。また、新技術への適応も課題で、長年進めてきた会員管理システム(AKSO)の更新計画は難航しており、ウェブサイト改革も遅れが指摘されています。加えて、近年は会員数こそ微増しているものの会費収入が減少傾向にあり、2024年予算では45,000ユーロの赤字が見込まれるなど財政面での課題も抱えています(投資活動により黒字転換したとの報告もあります)。その一方で、新型コロナ禍には初の「バーチャル世界大会」を2020年に開催し、世界中から1,800人以上が参加するなどオンラインでの結束を図りました。このようにUEAは、グローバルな発信力と組織基盤の強化に努め、エスペラント運動全体を牽引しています。
無国籍・無政府主義的立場の伝統を持つ SAT(Sennacieca Asocio Tutmonda) も、着実に活動を続けています。 2020~2022年はオンライン形式で年次大会(SAT-Kongreso)を開催し、2023年にはフランスのグレジヨン城で約55名が参加する対面大会を実現しました。これは3年ぶりの対面開催で、参加者はヨーロッパを中心に4大陸から集まりました(残念ながらアフリカからの参加者はゼロ)。大会では機関紙『Sennaciulo(センナチウーロ)』の編集方針や組織規約の改定について討議が行われたほか、各種分科会も活発に開催されています。講演テーマも西サハラ問題や欧州の難民、ジュリアン・アサンジ氏の扱いなど社会的・政治的案件が多く、エスペラントを介した国際的な連帯と社会正義の追求というSATの理念が色濃く反映されています。少人数ながらも、こうした草の根の活動がエスペラント文化の多様性を支えています。
TEJO(Tutmonda Esperantista Junulara Organizo) はUEAの青年部にあたる組織で、若者ならではの視点からエスペラント運動を活性化させています。近年特に力を入れているのが気候変動や多様性といった社会課題への取り組みです。例えば2021年には欧州評議会の支援を受けて「気候正義: 我らの地球、我らの権利、我らの未来」と題する研修セッションを企画し、持続可能な社会と人権についてエスペラント青年が学ぶ機会を提供しました。併せて「多様で平等: 多文化共生教育」というテーマの研修も行い、差別解消やインクルージョンについて議論しています。こうした国際ワークショップを通じ、TEJOは気候正義や言語多様性など現代的トピックにエスペラント青年が参画する道を開いています。また、国際連合やUNESCOの場でもUEAと連携し若者の立場から発言するなど、「若者の権利」 の代弁者としての役割も果たしています。内部的には機関誌『コンタクト(Kontakto)』の発行やオンラインニュースレター「TEJO Aktuale」の配信を通じて、世界中のエスペラント青年をゆるやかにネットワークしています。近年は休止していたエスペランティスト招待所ネットワーク「Pasporta Servo」の再活性化や、育成プログラムの開催など、次世代リーダー育成にも注力しています。国際大会(IJK)の開催と合わせ、TEJOはエスペラント運動に若いエネルギーと社会的意義をもたらしています。
エスペラント教育の専門家団体である ILEI(Internacia Ligo de Esperantistaj Instruistoj) は、語学教育分野での地道な活動を続けています。コロナ禍には年次大会やシンポジウムをオンライン開催し、デジタル技術を活用した教授法や教材開発について世界各国の教師が知見を共有しました。2022年以降は対面イベントも再開し、興味深い試みとして2023年の年次大会はイタリアでの国際青年大会(IJK)と同時併催されました。同じ会場にエスペラント教師と若い学習者が集うことで世代間交流が生まえ、教育と普及活動の連携が図られています。このようにILEIとTEJOの協力関係が強まっているのも近年の特徴です。さらに、UEAおよびTEJOと共同で国際教育デーに関する声明を発表するなど、エスペラントによる母語教育支援や言語権の重要性をアピールする活動にも関わっています。刊行物では教育専門誌の発行や学習者向け雑誌『Juna Amiko』の編集を続け、オンラインでも教育者向けのウェビナーや講座を開催して教師の力量向上を支えています。こうした活動を通じ、ILEIはエスペラント教育の質を高め、学校や学習者コミュニティへのエスペラント浸透に努めています。
エスペラントの国際イベントも、この数年で開催形式やテーマに新たな潮流が見られます。パンデミックを経て対面とオンラインを組み合わせたハイブリッド型が定着しつつあり、開催地の多様化や扱う話題にも現代性が反映されています。主要なイベントの近況を見てみましょう。
世界エスペラント大会(UK) – エスペラント最大の年次大会であるUK(Universala Kongreso)は、2020年と2021年に通常の対面開催ができなかったため、UEA主催でバーチャル大会が実施されました。初回の2020年バーチャルUKにはなんと1,852人ものエスペランティストがオンライン登録し、時差を超えて24時間途切れないプログラムが提供される画期的な試みとなりました。その後、107回大会(2022年モントリオール)で3年ぶりに対面形式が復活し、世界各地から数百人規模の参加者が集まりました。モントリオール大会は40年ぶりの北米開催であり、エスペラント運動史に残る出来事として記憶されるでしょう。続く 108回大会(2023年トリノ) には1,319名の登録があり、一部プログラムのオンライン中継も行われるなどハイブリッド要素も加わりました。また2023年大会ではロシアからの参加者がわずか1名に留まる一方、翌年の開催地がアフリカと決まったことで多数のアフリカ人エスペランティストがビザを取得して来場し、会場で2024年大会(タンザニア・アルーシャ)の宣伝活動を行う光景も見られました。109回大会(2024年アルーシャ)は史上初めてサハラ以南のアフリカで開かれる予定で、そのテーマも「人々と言語と環境-より良い世界のために」と掲げられており、地域・内容の両面で多様性を拡大する方向にあります。
国際エスペラント青年大会(IJK) – 世界中の若いエスペランティストが集うIJKも、2020年はオンライン開催(イベント名「Retoso」)で凌ぎ、2022年にオランダで対面復活しました。2022年大会(第78回)には233名が参加し、その約4分の1が初参加者でした。2023年の第79回大会はイタリアで開催され、前述のILEI大会と合同で行うという新しい試みに踏み切っています。次回2024年の開催地選定を巡っては、当初候補に挙がったアフリカ(タンザニア)案とヨーロッパ(リトアニア)案で議論が起こりました。アフリカ開催は「欧州偏重を是正し現地の若者運動を支援すべき」との意見が出た一方、「世界大会(UK)と併催になるとIJKの独自性が損なわれる」との懸念も示されました。最終的に第80回大会(2024年)はリトアニア開催に決まりましたが、この議論は若手世代が地理的多様性やイベントの在り方を模索していることを物語っています。なおTEJOはオンラインイベント「Retoso」をコロナ後も継続しており、年に一度、対面IJKに参加できない若者も含め気軽に集える場を提供しています。リアルとオンライン双方で若者コミュニティを維持する工夫が進んでいます。
NASK(北米エスペラント夏期講習会) – アメリカ合衆国で50年以上の歴史を持つエスペラント集中講習会NASKも、この数年で開催形態を柔軟に変化させました。2020年には通常の対面合宿をオンラインに切り替えた結果、例年の3倍もの受講者が集まった例もあり、リモート形式が新規学習者の裾野を広げる効果を示しました。近年は春季にオンライン講座を開講し、夏には短期の対面合宿を実施するハイブリッド型となっています。2023年も春にオンラインコース(講師:ラファ・ノゲラス氏ほか)を行い、7月にノースカロライナ州で5日間の対面講習を開催しました。初級から上級まで複数レベルのクラスを設け、著名な講師陣(上級クラスは現UEA会長のダンカン・チャータース氏が担当)の指導の下で学べる貴重な機会となっています。このようにNASKはオンライン学習を組み合わせることで参加ハードルを下げつつ、対面の濃密な語学体験も提供し、北米地域の学習コミュニティを支えています。
Komuna Seminario – アジアのエスペラント若者団体が持ち回り開催する Komuna Seminario(コムーナ・セミナリーオ) も注目すべきイベントです。中国・日本・韓国・ベトナムの青年エスペランティストが毎年一堂に会し、文化交流や議論を行うこのセミナーは、パンデミック中の2021年と2022年はオンライン開催となりました。しかし第41回(2023年)は現地開催に戻り、12月にベトナムのハノイ及びニンビンで開催されています。アジアでは最大規模のエスペラント青年イベントであり、2023年のテーマは「テクノロジーの急速な発展が我々の生活に与える影響」でした。このテーマ設定からもうかがえるように、単に語学交流だけでなく現代社会の課題について議論する場にもなっています。東アジア各国の若者が言語を超えて意見交換し友情を育むKomuna Seminarioは、地域におけるエスペラント文化の発展とコミュニティ強化に大きく貢献しています。
エスペラント運動のもう一つの大きな変化は、SNSやアプリを通じたコミュニティ形成です。特に若い世代のエスペランティストはインターネット上で積極的に交流し、新しい学習者もデジタルツール経由で世界に加わっています。
TwitterやFacebookといった従来型SNSに加え、近年は Reddit や Discord 上に大規模なエスペラントコミュニティが出現しています。たとえば英語圏の匿名掲示板Redditの 「r/Esperanto」 サブレディットには、現在およそ32,000人のメンバーが登録しており、日々質問への回答や学習相談・雑談が行われています。Discordでもエスペラント専用サーバーが人気で、最大のサーバーには8千人を超える参加者が集っています。これらのオンラインコミュニティでは、ミーム画像を使った気軽な投稿から真剣な文法議論まで幅広い話題が飛び交い、初心者も上級話者も垣根なく交流しています。特筆すべきは、その即時性とグローバルな広がりです。投稿すれば数分で世界中の仲間から返信がもらえる環境は、地理的に分散したエスペラント話者同士を以前にも増して強く結びつけています。またInstagram上でも #esperanto などのハッシュタグで学習アカウントやエスペラント句を紹介する投稿が増えており、YouTubeでも「Evildea」などエスペラント系YouTuberによる教材動画・ vlogが人気を博しています。こうしたSNS上の盛り上がりは若年層にエスペラントを広める原動力となっており、「エスペラント文化」をオンライン空間にも根付かせつつあります。
スマートフォンの普及に伴い、エスペラント学習者は専用アプリからも急増しています。中でも無料語学アプリ Duolingo はエスペラント人気を飛躍的に押し上げました。2015年に英語話者向けのエスペラントコースが登場して以来、累計で数百万がコースを開始し、2022年時点で約30万のアクティブ学習者がいると報告されています。一時はスペイン語話者向けやポルトガル語話者向けコースも提供されましたが、運営上の理由で2023年初頭にこれらは終了し(英語話者向けコースは継続中)、現在も世界中の初心者が英語ベースのコースでエスペラントを学んでいます。
実際、Duolingoでエスペラントを学び始めた「パンデミック世代」の若者が、そのままオンラインコミュニティに参加したり国際大会に足を運ぶケースも増えました。加えて、総合学習サイト Lernu.net には2018年時点で登録者32万人を超えるなど、ウェブ教材による独習環境も充実しています。学習段階を終えた人々が実践練習に使っているのが、エスペラント話者検索アプリ Amikumu です。GPSを利用して近くのエスペランティストを表示してくれるこのアプリには2020年時点で既に2万人以上のユーザーがおり、その約3分の2がエスペラント話者でした。今ではさらに数を増やし、旅行先でもワンタップで現地の仲間を見つけて直接会話を楽しむ、といったことも容易になっています。こうしたアプリ利用の実態を見ると、エスペラント学習〜実践までのサイクルが格段に回りやすくなっていることがわかります。時間や場所の制約を超えて学び・出会えるデジタルツールは、21世紀のエスペラントコミュニティ発展に不可欠な基盤となっています。
デジタル世代のエスペランティストは、エスペラントを国際共通語として使うだけでなく、現代社会の課題に積極的に関わる動きを見せています。前述のようにTEJOは気候正義(klimata justeco)や言語権(lingvaj rajtoj)、多様性(pluraneco)といったテーマで国際セミナーや研修を開催し、各国の若者がエスペラントを介して問題意識を共有する場を作り出しました。例えば気候変動に関する欧州青年センター(ストラスブール)での研修では、「持続可能な社会と人権」「気候危機と言語の役割」といった内容をエスペラントと英語で学び、各国の若手活動家が自国で環境問題に取り組むスキルを身につけました。またジェンダー平等や平和教育についても議題に挙げ、エスペラントが「世界の若者をつなぐ共通基盤」として機能しています。さらに、国連の持続可能な開発目標(SDGs)実現に向けたユースフォーラムにエスペラント青年代表が参加するなど、エスペラント運動の若年層は他言語の活動家とも連帯しながら国際社会で存在感を示しつつあります。こうしたプロジェクトは、エスペラントが単なる語学趣味を超えて地球規模の問題解決に貢献し得ることを示す好例です。その背景には、「エスペラントの理念(平等なコミュニケーション)は現代の諸課題にも通じる」という信念があります。実際、UEAとTEJOは世界各国語の平等と多言語主義を推進する立場から、文化的多様性や母語教育の重要性を繰り返し訴えています。エスペラント青年たちが気候マーチに参加したり、オンラインで多文化交流イベントを開催する機会も増えており、「エスペラント文化」はより社会参加型で開かれたものへと発展しています。
以上のように、エスペラント運動は伝統を守りつつも新しい時代に合わせて変化を遂げています。主要団体は組織運営の刷新や社会への発信を強化し、国際イベントは柔軟な形式と多彩なテーマで参加者を魅了しています。特に若い世代がSNSやアプリで築くコミュニティは、エスペラントの学習・実践環境を一変させました。創始から一世紀以上経たエスペラントですが、その文化活動はむしろ現在進行形で拡大しており、言語の壁を越えた絆づくりや社会貢献の可能性を示し続けています。各地のエスペランティストたちが培ってきた国際連帯の精神は、デジタル技術や新たな価値観と結びつくことで一層輝きを増し、今後も私たちにユニークで興味深い物語を提供してくれるでしょう。
20 世紀初頭にはエスペラント組織が次々と設立されました。中でも代表的なものには次のものがあります。
Universala Esperanto-Asocio (UEA):1908 年に創設され、エスペラントの普及と国際交流を促進する世界最大のエスペラント団体。
Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT):1921 年に創設され、政治や社会問題の議論を重視する無国籍世界協会。特に労働者階級の国際的連帯を目指す。
Akademio de Esperanto:1905 年に発足し、エスペラントの正則性を維持しつつ言語の自然な発展を促進するための言語アカデミー。規範の決定や語彙の整理を行う組織。
エスペラント運動は、20 世紀初頭の各国で抑圧や迫害を受けることがありました。
ソビエト連邦:1920 年代から 1930 年代にかけて、スターリン政権はエスペランティストをスパイとみなして弾圧し、多くのエスペランティストが逮捕され、処刑されました。
ナチス・ドイツ:ヒトラーの『我が闘争』では、エスペラントをユダヤ人による国際陰謀の道具と見なす主張がなされ、エスペランティストは迫害されました。
戦後東欧:社会主義体制下でエスペラント活動はしばしば監視や弾圧の対象となりました。特にチェコスロバキア、ハンガリー、東ドイツなどでは、エスペランティストがスパイ活動を行っていると疑われ、取り締まりが行われることがありました。ただし、これらの国々ではエスペラントの使用が完全に禁止されたわけではなく、一定の制約下で許可されることもありました。第二次世界大戦後、エスペラント運動は大きく復興しました。特に Universala Esperanto-Asocio (UEA) は戦後の国際会議での活動を強化し、エスペラントを国際連合に提案する運動も行いました。また、1954 年の UNESCO 総会でエスペラントが文化交流の手段として公式に認められたことは大きな成果でした。
一方で、労働者階級や社会的平等を重視する SAT も引き続き活動を続け、特に左派的な思想を持つエスペランティストの中で支持を集めました。
また、エスペラント文学の発展も重要な要素です。特に戦後には、William Auld や Kálmán Kalocsay らが多くの詩や文学作品を発表し、エスペラント文化の一翼を担いました。
現代においては、インターネットの普及によってエスペラントの学習や使用が以前よりも容易になり、Duolingo などのプラットフォームによって新たな学習者が増加しています。エスペラント運動は、文化活動と国際交流を通じて今も成長を続けています。
エスペラント運動は数多くの団体によって支えられています。ここでは代表的な組織について紹介します。
1908 年に創立され、世界最大のエスペラント団体として活動しています。UEA はエスペラントの普及と文化交流を促進することを目的としており、毎年 Universala Kongreso (UK) と呼ばれる世界エスペラント大会を開催しています。また、国際連合や UNESCO との連携活動も行っています。
1921 年に設立された無国籍世界協会(SAT)は、エスペラントを通じて労働者階級の国際的連帯を目指す組織です。文化的および社会的な問題について議論し、特に左派的な思想を持つエスペランティストによって支持されています。年次大会である SAT-Kongreso は多くの活動家を引きつけています。
若者を対象とするエスペラント組織で、UEA の青年部として活動しています。TEJO は世界各地の若年層のエスペランティストを結びつけ、毎年 Internacia Junulara Kongreso (IJK) を開催しています。オンライン活動や交流プログラムも盛んです。
日本におけるエスペラントの普及を目的とする組織で、教育活動や普及活動を行っています。日本エスペラント大会などを開催し、日本国内でのエスペラントの活用を推進しています。
エスペラント教師のための国際組織で、エスペラント教育の質向上と普及を目指しています。教師向けの教材開発や、教育法の研究なども行っています。
1968 年に設立されたエスペラント研究財団は、エスペラントと国際的コミュニケーションの学術研究を支援することを目的としています。特に教育プロジェクト(例えば NASK)やインターネットを利用した普及活動に力を入れています。また、エスペラント研究を推進するための奨学金や助成金を提供するなど、学術的な分野で重要な役割を果たしています。
エスペラント運動において、国際大会やイベントは重要な役割を果たしています。ここでは主要なイベントについて紹介します。
毎年開催される世界エスペラント大会で、世界各国から数千人のエスペランティストが集まります。文化交流、講演、討論会、エスペラント教育に関するセッションなどが行われる最大のイベントです。
TEJO が主催する若者向けの国際大会で、毎年異なる国で開催されます。エスペラントを話す若者たちが集まり、文化活動、ワークショップ、観光などを通じて交流を深めます。
北米で行われるエスペラント集中講座で、特に学習者と教師の交流の場として重視されています。教育プログラムが充実しており、初心者から上級者まで幅広く参加できます。
1980年代に始まり、中国、日本、韓国を中心としたアジアの若年エスペランティストによって毎年開催される交流イベントです。文化交流や学習活動を通じて、アジア地域のエスペランティスト間の結びつきを深める役割を果たしています。
アジア大会、ヨーロッパ大会、日本エスペラント大会など、各地域で開催される大会も数多く存在します。特に日本では 日本エスペラント大会 が毎年開催され、国内外からの参加者が集まります。
エスペラントイベント自体はほぼ毎週どこかで開催されています。毎日更新される Eventa Servo を活用してください。
エスペラントは単なる言語ではなく、豊かな文化表現の媒体でもあります。ここではエスペラント文化に関連する代表的な分野について紹介します。
エスペラントによる創作文学は、詩、短編小説、小説、エッセイといった幅広いジャンルで発展しています。特に戦後には、William Auld や Jorge Camacho、Kálmán Kalocsay らが多くの優れた作品を発表しました。また、Julio Baghy は感動的な詩や劇作品で知られています。
エスペラントは多くの文学作品の翻訳にも使用されてきました。世界各国の名著がエスペラントに翻訳され、エスペラント話者が様々な文化に触れる機会を提供しています。また、Claude Piron は翻訳者としても活動し、特に心理学やエッセイの分野で著作を残しています。
エスペラントによる音楽活動も盛んであり、音楽グループや個人アーティストがエスペラントでの歌を制作しています。また、劇や映画もエスペラントで製作されることがあり、特にアマチュア劇団による公演が活発に行われています。
William Auld:エスペラント文学の巨匠とされる詩人で、特に『La Infana Raso(子供の人種)』が名作とされる。
Claude Piron:作家、翻訳者、心理学者としても活動。エスペラント文学に数多くの短編小説やエッセイを残した。
Julio Baghy:感動的な詩と劇作品で有名。特に人間性や平和をテーマとする作品が評価されている。
エスペラント文化は、文学や音楽だけでなく、さまざまな創作活動を通じて発展し続けています。
エスペラントの文化活動は、雑誌や書籍、オンラインメディアなどを通じて広く展開されています。ここでは代表的なメディアと出版活動について紹介します。
エスペラント関連の雑誌や定期刊行物は、エスペラント運動の発展に重要な役割を果たしてきました。
『Esperanto』:Universala Esperanto-Asocio (UEA) によって発行される月刊誌で、エスペラントに関するニュース、文化、教育、国際交流に関する記事を掲載。
『Monato』:一般のニュースをエスペラントで伝える月刊誌で、世界中のエスペランティストによって書かれた記事が集まる。
『Sennaciulo』:Sennacieca Asocio Tutmonda (SAT) によって発行される機関紙。特に社会問題や政治問題についての論評が掲載される。
『エスペラント/La Revuo Orienta』:Japana Esperanto-Instituto (JEI) によって発行される月刊誌で、エスペラントに関するニュース、文化、教育、国際交流に関する記事を掲載。
エスペラント文学や研究書の出版も盛んです。世界各国の文学作品がエスペラントに翻訳されるだけでなく、エスペラントによるオリジナル作品も多数発表されています。主な出版社には次のものがあります。
Flandra Esperanto-Ligo (FEL):ベルギーを拠点にした出版社。幅広いジャンルのエスペラント書籍を刊行。
Universala Esperanto-Asocio (UEA):エスペラント関連の重要な文献を出版。
Kava-Pech:チェコを拠点とする出版社で、特に学習書やエスペラント文学を出版。
Sezonoj:ロシアのエスペラント出版社で、文学やエッセイなどを発行。
Mondial:アメリカを拠点とする出版社で、エスペラント文学や学術書、教育書を出版。
Japana Esperanto-Instituto (JEI):日本でのエスペラント関連書籍の出版を行い、特に学習書や教育資料に強い。
日本エスペラント図書刊行会:日本国内でエスペラントの普及を目的とする出版社。文学作品や学習書を多く出版。
インターネットを通じたエスペラントの普及も活発に行われています。ブログ、ポッドキャスト、YouTube チャンネルなどが存在し、新しい学習者や文化活動の紹介に役立っています。
ポッドキャスト:エスペラントに関するニュースやインタビューを提供する番組が増えつつあります。
動画とブログ:YouTube での教育動画やエスペランティストのブログも人気があります。
エスペラントメディアは、伝統的な紙媒体だけでなく、デジタルメディアを通じても急速に拡大しています。
インターネットはエスペラント普及の重要なツールとなり、多くのプラットフォームがエスペラント学習とコミュニケーションを支援しています。
Duolingo:エスペラント学習コースを提供する人気のプラットフォーム。特に英語話者向けのエスペラントコースは多数の学習者を獲得し、世界中に新たなエスペランティストを生み出しています。
Amikumu:エスペラント話者を見つけて交流することを目的としたモバイルアプリ。地理的に近くにいるエスペランティストを見つけ、直接会うことが可能です。
Reddit:エスペラントに関する掲示板(特に r/esperanto)が存在し、質問やディスカッション、イベント告知などが行われています。
エスペラントは国際的な旅行や宿泊の分野でも活用されています。
Pasporta Servo:エスペラント話者による無料宿泊ネットワークで、世界中のエスペランティストが提供する宿泊場所を利用できます。旅行者とホストの双方がエスペラントを通じてコミュニケーションを行い、文化交流を深める手段となっています。
近年、エスペラントを学ぶ若年層の増加が見られます。特にインターネットを介した学習ツールの普及や、SNS でのコミュニティ形成が重要な役割を果たしています。
若年層の活動:TEJO(Tutmonda Esperantista Junulara Organizo)の活動を中心に、若者向けの国際大会やオンラインイベントが盛んに行われています。
ネットワーク形成:オンラインフォーラム、Discord サーバー、YouTube チャンネルなどを通じて、エスペラント学習者同士がつながりを持ちやすくなっています。
インターネットの普及により、エスペラントコミュニティは以前よりも多様化し、アクセスしやすくなっています。エスペラントの未来は、これらの新しいツールやネットワークを通じてさらに発展する可能性があります。
Markobutonoj () utilas por ekzerci vin en Ekzercejo
| Vorto | Baza formo | Difino | 17.2 | 172 | … |
|---|---|---|
| エスペラント運動の近年の文化活動とコミュニティ発展 | エスペラント運動の近年の文化活動とコミュニティ発展 | … |
Kajero
Multlingva vortaro
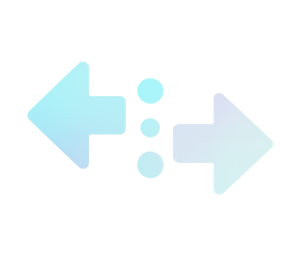
Per
Cainia 3.1 双向推理系统

Programita de
Sato kaj Cainiao 2019-2025 Subtenu nin per taso da kafo

Funkciigata de
SWI-Prolog
Babilejo